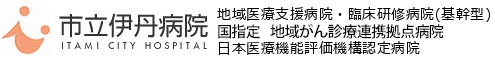認知症疾患医療センター(もの忘れ外来)
当院は、令和2年10月1日に「認知症疾患医療センター(地域型)」に指定されました。
| 医師名 | 役職 | 学会専門医・認定医 |
|---|---|---|
| 中村 好男 | 診療部長 兼科主任部長 兼地域医療連携室主任部長 兼認知症疾患医療センター長 |
日本認知症学会[認知症専門医][指導医] 日本老年医学会(代議員)[老年科専門医][指導医] 日本内科学会[認定医][総合内科専門医][指導医] 日本腎臓学会[専門医] 日本医師会[認定産業医] 大阪大学医学部臨床教授 認知症サポート医 がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会終了 |
| 伊東 範尚 | 科部長 兼臨床研修センター副センター長 兼地域医療連携室部長 |
日本認知症学会[認知症専門医][指導医] 日本老年医学会(代議員)[老年科専門医][指導医] 日本内科学会[認定医][総合内科専門医][指導医] 日本高血圧学会[高血圧専門医][指導医] 日本プライマリ・ケア連合学会[認定医][指導医] 日本循環器学会[専門医] 日本睡眠学会[専門医] 日本サルコペニア・フレイル学会[指導士] がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了 認知症サポート医 |
| 尾﨑 和成 | 科部長 | 日本老年医学会[老年科専門医] 日本認知症予防学会[専門医] 日本内科学会[認定医][指導医] 日本東洋医学会[漢方専門医] がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了 認知症サポート医 |
| 医師名 | 役職 | 学会専門医・認定医 |
|---|---|---|
| 三好 崇文 | 科主任部長 兼心療内科主任部長 兼緩和ケアセンター次長 兼臨床心理センター長 |
日本精神神経学会[専門医][指導医][学会認定認知症診療医] 日本総合病院精神医学会[専門医][指導医] 日本認知症学会[専門医][指導医] 日本サイコオンコロジー学会 学会認定精神腫瘍医 精神腫瘍学の基本教育に関する研修会修了 「緩和ケア研修会」集合研修企画責任者 がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会修了 |
認知症疾患医療センター(地域型)とは
認知症疾患医療センター(地域型)は、認知症の保健医療水準の向上を促進するために、都道府県及び指定都市が設置する専門医療機関です。
認知症疾患医療センターでは、地域の認知症医療の中核として、認知症疾患に関する鑑別診断とその初期対応、認知症の行動・心理症状と身体合併症への急性期対応、専門医療相談、診断後の相談支援等を実施するとともに、地域保健医療・介護関係者への研修等を行っています。
専門医療相談(電話・面談)
専門の職員が認知症に関する相談を受けます。
相談は無料です。面談での相談を希望される場合は電話で予約が必要です。
*認知症疾患医療センター専用電話*
072-767-7119
受付時間:月~金曜(祝・休日除く)
午前9時~正午、午後1時~4時
認知症疾患医療センターの「もの忘れ外来」の受診までの流れ
本人・家族がかかりつけの医療機関へ相談
かかりつけ医の診療科目は問いません。
(※かかりつけ医がない場合は、認知症疾患医療センター専用電話072-767-7119へご連絡をいただけましたら、近隣の診療所・クリニックの情報を提供させていただきます。)
↓
かかりつけ医療機関から予約(完全予約制)
かかりつけの医療機関からFAXで診療情報提供書(紹介状)を送信ください。
FAX番号:072-777-8277(地域医療連携室直通)
↓
かかりつけの医療機関から予約票を受け取る
当院がかかりつけの医療機関へ予約票をFAX(またはメール)します。
↓
当院の認知症疾患医療センター「もの忘れ外来」を受診する
・受診日には、①紹介状の原本、②お薬手帳、③予約票、④健康保険証などを持参してください。
・問診・診察・検査をしますので、時間には余裕をもって来院ください。
・通常は、鑑別診断の結果まで数回受診をしていただくことになります。
指定を受けた理由
伊丹市は、早くから医師会が中心となって認知症診療連携システムを運用しています。まず、かかりつけ医が相談窓口「認知症かかりつけ医」となって早期発見に努め、専門的な検査や治療が必要な場合は「認知症専門医療機関」へ紹介して迅速な治療へ繋げます。当院の老年内科は、認知症専門医療機関の一つとして登録され、これまでも認知症の鑑別診断と初期対応を行ってきました。
また、当院は地域医療支援病院として高齢者救急を受け、認知症のある人の身体合併症の急性期治療に対応しています。高齢者は入院中にせん妄(意識障害)を生じたり、認知症のある人では行動心理症状が現れたりして身体疾患の治療に支障をきたすことがあります。老年内科を中心とする多職種協働の認知症ケアチームがせん妄や周辺症状に対応しています。
これらの実績が評価され、県知事の指定を受けました。
認知症高齢者にやさしい地域づくりの拠点として
当院の特徴は、老年内科が中心となって高齢者の生活を重視していることです。食事や歩行、トイレ、入浴などの日常生活、買い物、家事、金銭や薬の管理などの社会生活、健康、生きがい、快適さなどの生活の質を目安としています。
認知症を単に病気として治療するだけでなく、認知症があっても本人や家族が穏やかに過ごせることが大切だと考え、院内では看護師、セラピスト、臨床心理士、薬剤師、管理栄養士、ソーシャルワーカーなど多職種と協働しています。
認知症疾患医療センターとして、地域住民の皆さん、かかりつけ医などの医療機関や介護・福祉施設、地域包括支援センター、行政機関とよりいっそう連携を深めていきます。
お問合せ
認知症疾患医療センター 専門電話 072-767-7119
(月~金曜(祝・休日除く)の午前9時~正午、午後1時~4時)
※受診にはかかりつけ医からの紹介状が必要です。詳しくはご利用案内をご覧ください。