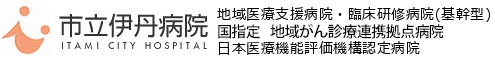呼吸器内科
| 医師名 | 役職 | 学会専門医・認定医 |
|---|---|---|
| 細井 慶太 | 科主任部長 兼リハビリテーション科部長 兼経営企画室部長 兼呼吸器アレルギー診療センター長 |
日本内科学会[総合内科専門医][指導医] 日本呼吸器学会[専門医][指導医] 日本呼吸器内視鏡学会[気管支鏡専門医][指導医] 日本がん治療認定医機構[がん治療認定医] 日本ぜんそく学会[認定専門医] 日本救急医学会会員認定 ICLS・BLSコースディレクター 大阪医科薬科大学臨床教育教授 ICLSディレクター /JMECCインストラクター がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修修了 |
| 木下 善詞 | 科部長 兼感染対策室主任部長 |
日本内科学会[総合内科専門医][指導医] ICD制度協議会[ICD] 兵庫医科大学臨床教育教授 がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修修了 |
| 原 聡志 | 非常勤医 | 日本内科学会[総合内科専門医][指導医] 日本呼吸器学会[専門医][指導医] 日本血液学会[専門医][指導医] 日本がん治療認定医機構[がん治療認定医] 日本臨床腫瘍学会[がん薬物療法専門医][指導医] がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修修了 |
| 原 彩子 | 医長 | 日本内科学会[認定医][総合内科専門医] 日本呼吸器学会[専門医][指導医] がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修修了 |
| 髙田 悠司 | 副医長 |
日本内科学会[専門医] がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修修了 |
亀井 郁恵 | 副医長 |
日本専門医機構[内科専門医] がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修修了 |
| 石川 翔一 | 専攻医 | がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修修了 |
| 鈴木 淳史 | 専攻医 | |
| 吉田 夏紀 | 専攻医 | がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修修了 |
特色
令和 7 年の現在、スタッフ 5 名・専攻医 3 名・非常勤医 1 名の 9 名体制です。スタッフは呼吸器内科の範囲にとどまらず、腫瘍内科、感染症科などの専門領域に関心を広げ、各々が専門家としての技量の向上を続けています。呼吸器疾患に限らず、様々な病態を合併した患者さんたちにも内科医として十分対応できる体制を構築しようと努力しています。
治療実績
特徴
2024 年度に呼吸器内科医が担当して入院治療させていただいた患者さんはのべで 874 名です。この方々の退院時病名は表1に示す通りです。呼吸器疾患に限らず、多岐にわたった病名が挙がっています。この病名の分布に私どもの診療科の特徴が表れています。
呼吸器系に何らかの病態が存在する患者さんが主ですが、呼吸器系の疾患にとどまらず、全身性の感染症や腎尿路系の疾患、神経系疾患などにも内科医として携わっています。さらに、癌の診療では甲状腺癌や頭頸部癌、子宮体がん、精巣癌など様々な臓器の癌の患者さんにも、必要とされれば内科医として診療を提供させてもらっています。このような多様な病態の患者さんに満足頂ける医療を提供するためには、医師以外の医療提供者の協力が得られ
るチーム医療が必要です。
様々な技能や知識を備えたコメディカルの方々を統合する仕組みづくりを行っています。
呼吸器系に何らかの病態が存在する患者さんが主ですが、呼吸器系の疾患にとどまらず、全身性の感染症や腎尿路系の疾患、神経系疾患などにも内科医として携わっています。多様な病態の患者さんに満足頂ける医療を提供するためには、医師以外の医療提供者の協力が得られるチーム医療が必要です。様々な技能や知識を備えたコメディカルの方々を統合する仕組みづくりを行っています。
診療の内容
1.呼吸器感染症など
感染症治療の基本は1)正確な感染症の存在とその重症度の認知、2)問題の臓器と原因微生物の整理、3)1)2)に基づく適切な抗菌薬の選択・変更、4)適切な抗菌薬の効果の判定、であるといわれています。呼吸器感染症、尿路感染症に限らず的確な診断と治療への意思決定にはグラム染色が欠かせないとの観点から、できるだけ検体材料を適切に採取して染色検鏡する姿勢を中心に据えて感染症診療に取り組んでいます。当院では、COPDや気管支拡張症の急性増悪例も多く(表1参照)、喀痰のグラム染色、細菌培養、血液培養などの基本的な操作をできる限り省略しないで治療を進めることを行っています。
2.肺がん
肺がんは日本人のがん死において原因のトップとなりました。禁煙の啓発も進んで多くの公共施設で喫煙場所が撤廃されています。それでも肺がんはまだ増えています。肺がんの治療は、いま、日進月歩のただ中にあります。特に内科治療の中心をなす薬物療法は、革命のさなかにあります。免疫チェックポイント治療薬というこれまでにない発想で生まれた薬剤に、これまでの薬剤では見られなかったような劇的な効果が確認されてこの分野は活況を呈しています。当院は、腫瘍内科の専門医の資格を持つスタッフが早くからこの薬剤の適正な使用のための取り組みを指導してきており、新しい治療法の有効性とその限界を丁寧に検証してきています。さらに、呼吸器外科医、放射線科治療医とのカンファレンスを通しての協働によって癌患者さんにチームとして向き合っています。
3.気管支喘息/COPD(Chronic Obstructive Pulmonary Disease:慢性閉塞性肺疾患)
気管支喘息はありふれた病気で軽症例が多いので、多くはかかりつけ医の先生方のもとで治療されています。私どものところへは、かかりつけ医の先生方からの紹介で受診されます。あるいは、救急外来に喘息発作として受診されます。急性期でも安定期でも基本的な治療は、スパイロメーターを用いた的確な診断と、ピークフローモニターを基本に基づく吸入ステロイド治療を中心とした薬物療法による治療を行っています。最近は、重症喘息と呼ばれる難治例も多く、新たな治療にも取り組んでいます。さらに、慢性喘息という病気と付き合っていくためには、喘息という病気についてその病態をよく理解していただくことが必要です。ご自身の病気の理解が深まりますように出来る限り丁寧な説明を心がけて診療しております。COPD患者さんは風邪を引きますと喘息とそっくりな症状を示します。また、当院を紹介受診される方々は喘息との合併例である混合疾患が多く見られます。急性増悪で当院を紹介受診あるいは救急受診される方々は、ステロイドを用いた急性期治療を行った後に外来で吸入薬剤を中心とした安定期の治療に移ります。さらに安定すれば、かかりつけ医の先生方にお返しして経過観察となります。
4.慢性呼吸不全(結核後遺症を含む)
動いたときの呼吸困難をきたす病態は様々ありますが、酸素や炭酸ガスが関連した病態が呼吸不全です。酸素がうまく摂取できない病態(肺線維症が代表)はⅠ型呼吸不全と呼ばれています。酸素が足りない方には、酸素療法が必要になります。在宅酸素の提供環境が整っており、短期間の入院で適切な酸素投与の手順を決定して提供しております(数日の入院が必要ですのでかかりつけ医の紹介状が必要です)。炭酸ガスが上昇する病態はⅡ型呼吸不全と呼ばれています。このような方々には、その原因となる疾患によって治療の提供がさまざまになりますので入院して最適な治療(在宅酸素や在宅人工呼吸)の導入を提供いたします(やはり、入院が必要ですのでかかりつけ医からの紹介が必要です)。
5.間質性肺炎/肺線維症
間質性肺炎は治療の難しい病気です。多くは慢性リウマチなどのリウマチ関連疾患として発症します。そのほかには、特殊なアレルギー性の病気やウイルス性などの特殊な感染症などもあります。いずれも、入院して診断加療が必要です。アレルギー疾患・リウマチ科の先生方と密接に連携して、特殊な間質性肺炎の診断についても信頼できるレベルで医療が提供できていると自負しています。この領域の疾患のなかでは、特発性間質性肺炎/肺線維症にはまだ定まった治療の方法がありません。しかし、近年新しい抗線維化効果を持つ薬剤も登場し、有効な治療を計画・実施できる時代となって来ています。この疾患群は患者さんごとに個別の判断が特に必要であり、私どものチームとして現状での最適と思われる治療の提供ができるように努力しています。
6.肺結核・非結核性抗酸菌症
喀痰に結核菌が認められる排菌患者さんの治療は当院では原則として出来ません。活動性結核(排菌されている)患者さんは結核専門施設へ紹介しております。非結核性抗酸菌症は治療が難しいのですが、最近治療のガイドラインが提案されました。推奨される標準治療を当院でも行っています。約2年間の薬物治療が必要です。
7.睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群は、当院ではスクリーニングとしての簡易ポリソムノグラフを行っているのみです。精密検査は専門施設を紹介して、診断確定後のフォローの治療を行っています。
市立伊丹病院における肺がん登録事業について
当院は2012年より呼吸器内科治療症例を対象に、第6次全国肺癌登録事業に参加しています。
詳細はこちら 伊丹病院における肺がん登録事業について(PDF)